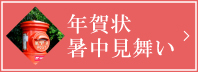顎関節症
| Q51 | 顎関節症の治療において、自分でできる療法はありますか? |
|---|
| A51 |
患者さん自身ができる療法として対象となるものは主に筋肉です。 1.筋肉を協調的に働かせること 2.間違った筋肉の使用法を矯正すること 3.動きの悪い関節の動きをよくすること 4.筋肉のリラクゼーションを覚えること 5.運動のスピードを増すこと
具体的には、「筋機能療法」、「筋肉のマッサージ」、「等尺性筋訓練法」などがあります。
※参考書籍 |
|---|
| Q52 | 筋肉のマッサージについて教えてください。 |
|---|
| A52 |
顎関節、その周りの筋肉の痛みや機能障害を訴える患者さんは、噛むときに使う筋、首や肩の筋に強い緊張を伴うことが多いです。このような場合、筋肉のマッサージは血流を促進し、筋肉を弛緩させ、緊張を取り去り、筋肉が協調的に働くことを目的としています。 筋肉は付着部位や形態が各々異なるため、それに応じたマッサージ方法が必要です。必ず左右対称に行い、疼痛を生じない程度の力で各筋肉を丁寧にもみほぐさなければいけません。マッサージはそれぞれの筋肉に3分から5分、1日3回行います。特に入浴時は効果的です。
1.咬筋のつまみマッサージ咬筋、内側翼突筋(噛むときに使う筋肉)のマッサージで、親指と人差し指を用い、下顎は力を抜き、痛みを感じるか感じないかという力で約3分間揉みほぐします。 2.後頸筋の回転マッサージ後頸筋(首の後ろの筋肉)は後頭部のうなじの部分をわずかに頭を前に傾斜させ、人差し指、中指、薬指を用いて大きく円を描くように回転させながらマッサージします。
3.側頭筋の母指球マッサージ側頭筋(左右頭の横にある筋肉)は頭をわずかに前傾させると共に下顎は安静位をとり、すべての筋の緊張を緩め、親指の付け根の大きなふくらみで痛みが感じない程度の力を用いて回転圧迫を3分間行います。
4.その他胸鎖乳突筋(首を左右に回す筋肉)のツマミマッサージも行うと首の柔軟性を得るために有効です。同時に頭の回転運動、柔軟運動も加えるとさらに有効です。
※参考書籍 |
|---|
| Q53 | 筋機能療法(トレーニング方法)について教えてください。 |
|---|
| A53 |
STEP1 正しい舌の位置を覚える舌の先を前歯の切歯、やや後方にあてる練習をします。 (この部分はスポットと呼ばれ、発音や唾を飲み込む際、舌の先を圧接、続いて舌の中央部に持っていくための重要なポイントになるところです) この時、矯正で使用するゴムを舌の先に置き、これが唾を飲み込むときに後方へ移動していないかをチェックします。舌を前に出す癖があるとゴムが後方に移動しますので、舌の癖があるかどうかのチェックに有効です。 ↓スポットの確認 ↓嚥下後にゴムが動いてなければ正しい嚥下が行われています STEP2 舌の中央部の上顎(口蓋)への圧接常に舌の先がどのような状況下でもすばやくスポットへの圧接が完全にマスターできているか否かを調べます。舌中央部の口蓋への圧接も最初はエラスティックバンドを使用し、唾を飲み込んだ後、鏡により移動がないことを確認します。
STEP3 舌の先、舌中央部、舌後方部の口蓋への圧接舌全体を口蓋上部に吸い付けたまま、下顎の開閉運動を行わせます。この際、舌小帯が一直線に真っ直ぐ張られていることを認識してもらい、上下顎の歯をかみしめていただき、ゆっくり唾を飲んでもらいます。
STEP4 舌の先をスポットにあて、舌全体を口蓋に圧接さらに、臼歯を噛みしめてゆっくりと唾を飲む訓練を行います。また、食物を噛む際スピードを徐々に増加し、リズミカルに噛み、唾を飲む訓練をします。練習する際は、デンタルフロスを下顎の犬歯と小臼歯にはさみ、これに舌が触れないように唾を飲みます。これができるようになれば完了です。 効果的に行うには、目立つ色のリマインダーマーカーやシール等を自分の生活の中で頻繁に目に付くところ、例えばドアのノブやテレビの前、机の上などに張り、これを見た瞬間に舌の先をスポットにあて、さらにゆっくり唾を飲むようにします。これが反射的にできれば効果はさらに上がってきます。
STEP5正しい唾の飲み方と舌の使い方が無意識にできるように日常の習慣づけを行います。
※参考書籍 |
|---|
| Q54 | 顎関節のゆがみを改善するために気をつけたらよいことはありますか? |
|---|
| A54 |
以下の生活習慣を見直すことで改善できます。 1.1日3食、腹6~8分を守って規則正しく生活するためにも、1日3食という基本原則は厳守しましょう。食事時間をしっかりとれば、生活リズムの乱れを防げるはずです。だから当然、間食は厳禁です。料理のジャンルは、日本人の歯やあごの構造に合うように考えられている和食がベストです。 2.睡眠時間は7時間以内に休日の日は寝だめしようと一日中ゴロゴロしていませんか?まず、休日もいつもと同じ時間に起きるということが基本です。「7時間眠れば十分」なのです。寝ている間の姿勢にもクセがあり、長く寝れば寝るほど体に悪影響がでます。「眠り以外には寝ない」も鉄則です。 3.1日1万歩以上しっかり歩く東京の成人サラリーマンの平均歩行量は1日7700歩だそうです。デスクワークが多いOLならその半分もいかないと思います。足の筋肉が衰えると、体がゆがみ、あごにもダメージが来ます。ダラダラ歩きはノーカウントです。両手を振って毎日1万歩を目標にしましょう。 4.甘いものや酒はほどほどに体によくないとわかっていても、つい手が伸びてしまうものには要注意です。ストレスや精神状態のゆがみで、簡単にストップがかけられなくなるのがこの類の嗜好品です。甘いものやお酒は食事のサイクルを狂わせ、余分な脂肪や糖分までも摂取することになってしまいがちです。なるべくなら手を出すのをやめましょう。 5.無理な運動、過剰な運動はしない運動とはそもそも無理な姿勢を強いるものです。成長期にひとつのスポーツだけをやらせることが禁止されていたときもあったと聞きます。大人とはいえやりすぎは禁物。普段忙しくてできないから、休日はムキになって過剰な運動をしてしまうこともあるでしょう。ムリな姿勢や動きは全身不調の原因になります。 6.○○しながら●●しない、「ながら」行動は絶対NG!例えば、食事をしながらテレビを見るという行為。当たり前のようにやっているのではないでしょうか?横を向いて食べれば、あごの筋肉にゆがみが表れてしまいます。食べることに集中できないから咀嚼もおろそかになってしまいます。なによりも行儀も悪い行為です。どんな“ながら”作業もゆがみの原因です。 ※参考書籍 |
|---|
| Q55 | 噛み合わせの悪さが肩や腰のコリにも深い関わりがある? |
|---|
| A55 |
噛み合わせのせいで肩コリになるというよりも、肩コリを起こす生活習慣の人は、顎にも無理な力をかけていて、その結果、噛み合わせが悪くなる、ということです。 女性なら、ハイヒールを履く、脚を組むといったあらゆる生活習慣が、顎への悪影響に。 なかでも、食事中の姿勢の悪さは何とかしないと。洋食ではテーブルに置いた皿に口を近づけ、うつむいて食べています。咀嚼面が斜めに傾いて、顎関節に負担がかかるんです。和食ならお茶碗を口元に運んで、背筋を伸ばして食べるでしょう。あの姿勢が本当はいいんです。 ※参考書籍 |
|---|
| Q56 | 左右均等に噛んだほうがよいのですか? |
|---|
| A56 |
体の歪みを補う“利きアゴ”をムリに直すとアゴが悲鳴をあげます。 よく耳にする「偏った噛み癖が顎関節症を招く」という話。それにはちょっと誤解があります。人間の体は左右どちらかに歪んでいるものですが、それを補うために派生したのが“利きアゴ”。「右ばかりで噛んでいた人がある時から無理に左で噛むと、アゴが痛い、口が開かないといった顎関節症に繋がる危険性が。利き手があるように、“利きアゴ”もあっていいのです。」 ※参考書籍 |
|---|
| Q57 | 歯並びが悪いと噛み合わせも悪いのですか? |
|---|
| A57 |
歯並びの見た目は悪くても、機能的に大きな問題はありません。 歯並びが悪い=噛み合わせが悪い、は間違った認識です。もともと尖っていた人間の歯は、使うごとに噛みやすいように表面がすり減り調整されていきます。見た目の悪さほど不便はないはずです。それなのに、アゴの発育期が終わった大人になって歯列矯正をすると、適合していたはずの噛み合わせにズレが生じて顎関節症になってしまうこともあります。「また最近では、顎関節症の治療に用いるスプリントもアゴに悪影響だといわれています」。18歳以上のアダルト矯正、スプリント治療は専門医とよく相談しましょう。 ※参考書籍 |
|---|
| Q58 | 顎関節症のチェック方法を教えて下さい。 |
|---|
| A58 |
今は平気でも突然起こる可能性もあります。 顎関節症予備軍度をチェックしてみましょう。
※参考書籍 |
|---|
| Q59 | 食事のときテレビを見ることはよくないと聞きましたが本当ですか? |
|---|
| A59 |
噛み合わせにとって、テレビを見ながらの食事はよくありません。とくに横向きの姿勢は、噛み合わせに悪い影響を与えます。 横向きでテレビを見ながら食事をしていると、目と首の動きにつられて、上顎はテレビの方を向いていますが、下顎は完全にその方向を向いておらず、上顎と下顎の位置、すなわち噛み合わせにずれが起こり、上と下の歯は、ずれた状態で接触してしまいます。毎日横向きでこのようなことをしていると、上の歯の裏側と下の歯がずれた状態で歯の磨耗が起こり、その結果顎がずれた状態で噛み合わせが合うようになっていきます。 一度顎がずれた状態で噛み合わせが固定すると、今度は横向きで食べることに違和感がなくなります。横を向くと顎はずれているが歯は噛み合っていて、正面を向くと顎はずれていないが噛み合わせがうまくいかないという状態になってしまいます。 したがって、噛み合わせをよくするには、成長期から正しい姿勢で食事をすることがとても大切なのです。 これと同じように、悪い姿勢が原因で、腰の具合が悪い、首が痛い、肩が凝るなどの症状が現れている場合、根本的な原因を治さずに顎だけに注目して正しく使おうとしても、よい噛み合わせをつくることはできません。生活習慣の乱れや悪い姿勢は噛み合わせをどんどん悪い方向にもっていってしまい、一度悪くなるとなかなか元には戻りません。噛み合わせは、日頃の生活習慣や姿勢の良し悪しなどによって、日々つくられているということをよく認識し、日頃からよい生活習慣とよい姿勢を身につけるようにしましょう。 ※参考書籍 |
|---|
| Q60 | “かみぐせ”は治したほうがよいのですか? |
|---|
| A60 | 噛み方にもクセがあります。左右の歯でバランスよく噛むのではなく、主として片側だけで噛むようなクセです。この“かみぐせ”は、治すべきかそのまま放っておいてよいのでしょうか?結論から先にいうと、治すにこしたことはないのですが、大人で“かみぐせ”はあるけれど噛むときの姿勢はきちんとしているという場合は、そのまま放っておいても大丈夫です。このような人の場合、長年に渡ってつくられてきたその人なりのバランスを無理に治そうとすると、かえって身体に負担がかかり、顎関節症を引き起こすことがあるためです。 骨や筋肉の発育における左右差には、成長する過程で姿勢の良し悪しが深く関係しています。ですので、片側で噛んでいることもまた、いままでの日常生活における姿勢のあり様の結果と考えることができるのです。そのため、根本的な原因である日常生活を正すことをしないで噛み方だけを変えようとすると、かえって無理をすることになり、顎関節症のような症状が現れてくるのです。 子供の頃から左右の偏りのない正しい姿勢で生活することは、左右の顎をバランスよく使うために必要なことです。しかし、すでに骨格の固まった大人が、生活様式はそのままで、噛み方だけ変えることは問題がすり替えられているだけのように思われます。 普段の姿勢に問題がある人の場合は、噛み癖を治すより先に姿勢を正すことの方が根本的かつ全体的な治療になります。そして姿勢がよくなってくると、噛み癖も良い方向に変わってくるのです。 ※参考書籍 |
|---|